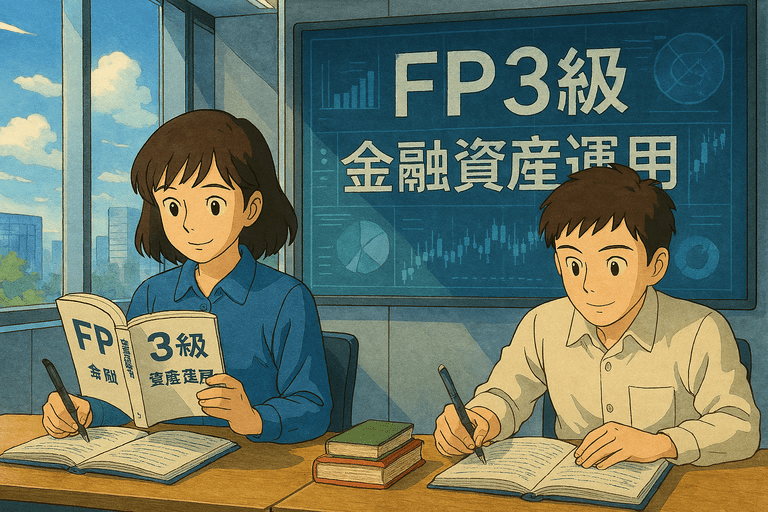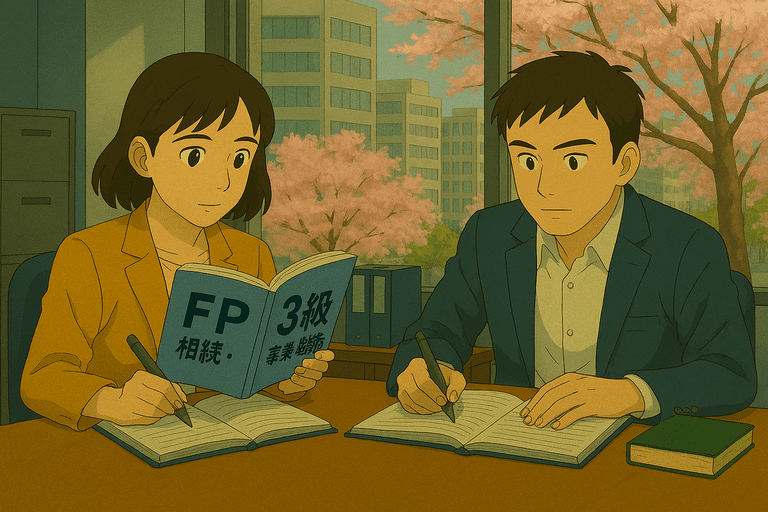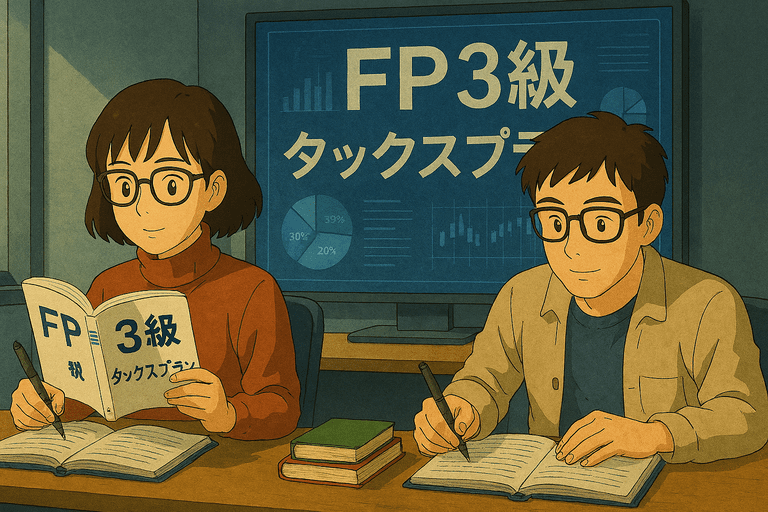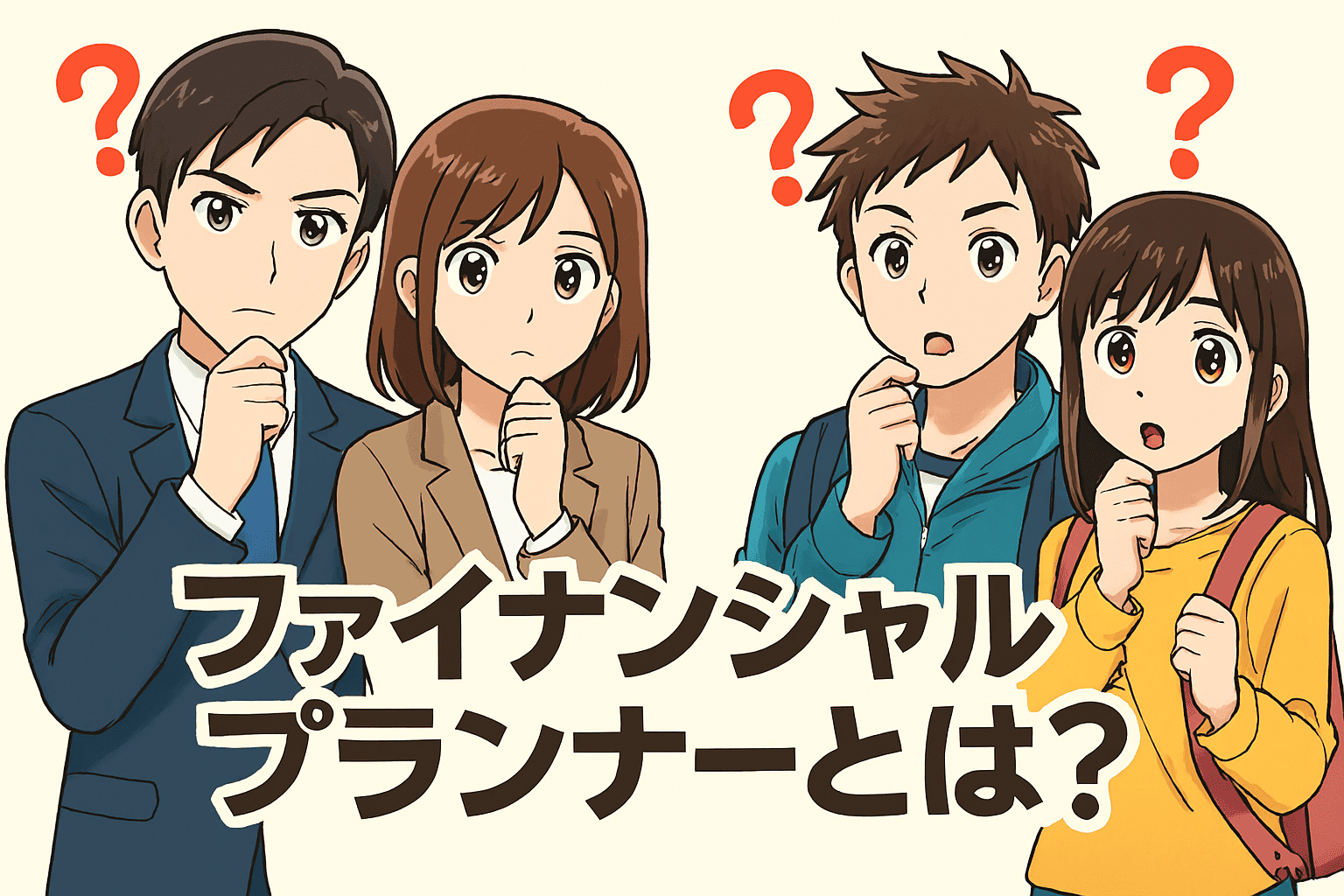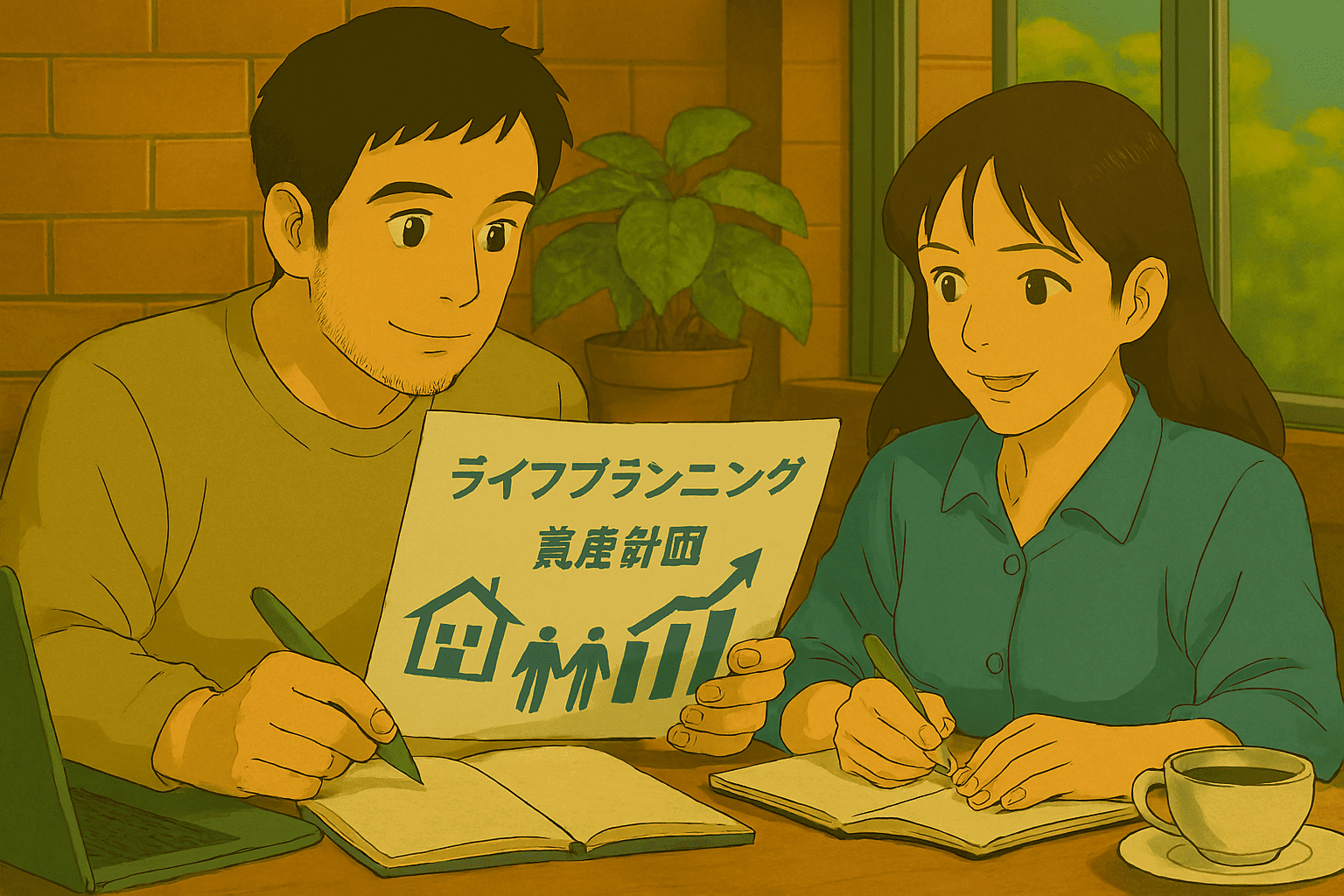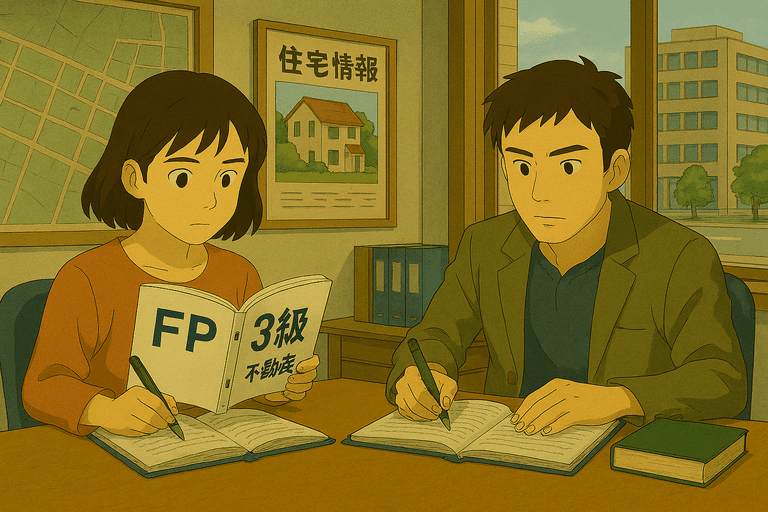FP3級 実技対策
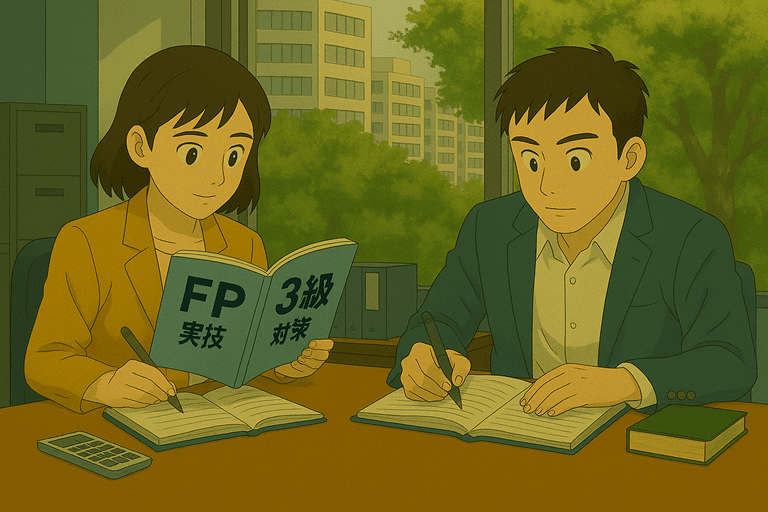
実技試験対策になります。
実際の相談業務を想定した問題を通じて、ファイナンシャルプランナーとしての「実務的な判断力」や「提案力」が問われます。単なる知識ではなく、事例に基づいた応用力がカギになります。
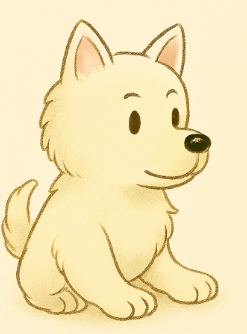
電卓で計算する問題が、必ず出題されます!
また、本試験はCBT(パソコンでのテスト)になるため、
パソコンの電卓機能で計算します。
パソコンの電卓でも練習しましょう!
FP3級の実技試験は、以下の2つの機関から選べます
| 実施機関 | 科目名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本FP協会 | 資産設計提案業務 | 幅広い分野から出題 初心者向けだが実家的取り組みやすい。 |
| 金融財政事情研究会 (きんざい) |
個人資産相談業務 保険顧客資産相談業務 |
より実務的で出題範囲が限定的。 保険業務を希望者におすすめ。 |
🕒 試験形式と時間
- 形式:マークシート方式(選択式)
- 時間:60分
- 合格基準:
- 日本FP協会:100点満点中60点以上
- きんざい:50点満点中30点以上
📈 合格率と難易度
- 合格率は70〜85%前後と高め
- 基本的な学習をしていれば、初学者でも十分合格可能
- 実技試験の方が学科試験よりも合格率が高い傾向あり
- 自分の興味や将来のキャリアに合わせて科目を選ぶ
(どちらか迷ったら、日本FP協会を選択するのが無難です)
頻繁に出題される計算問題(例)
P3級 実技「資産設計」頻出計算問題と解説
(1)退職所得控除の計算
問題例: 退職金800万円、勤続年数25年の場合の退職所得控除額と課税退職所得は?
解説:
①勤続年数が20年を超える場合:
控除額 = 40万円 × 20年 + 70万円 ×(25年 − 20年)
控除額 = 800万円
②課税退職所得 =(退職金 − 控除額)÷ 2
=(800万円 − 800万円)÷ 2 = 0円(課税なし)
(2)相続税の基礎控除額の計算
問題例: 法定相続人が3人の場合、基礎控除額はいくら?
解説:
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
= 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
(3)住宅ローン控除額の計算
問題例: 住宅ローン残高2,000万円、控除率1%の場合、初年度の控除額は?
解説:
控除額 = ローン残高 × 控除率
= 2,000万円 × 1% = 20万円
(4)生命保険料控除の計算(新契約)
問題例: 一般生命保険料を年間6万円支払った場合の控除額は?
解説:
新契約(平成24年以降)の上限は4万円
支払額が6万円の場合 → 控除額は 最大40,000円
(5)老齢基礎年金の月額試算
問題例: 満額受給で年間795,000円の場合、月額はいくら?
解説:
月額 = 年額 ÷ 12
= 795,000円 ÷ 12 = 66,250円
(6)ライフイベントに伴う支出の累積試算(キャッシュフロー表の問題)
事例: 結婚、住宅購入、子育て、教育、老後までの支出を時系列で試算する。たとえば、30歳で結婚、35歳で住宅購入(3,500万円)、40歳で子ども誕生、60歳で退職。
計算ポイント:
各イベントの支出を現在価値または将来価値で整理
住宅ローン返済、教育費、老後資金などをキャッシュフロー表に落とし込む
実技問題は、過去問を解いて理解しましょう!
- 過去問を活用して、出題形式に慣れることが重要
- 学科と実技は同日に受験可能。バランスよく対策しましょう!
- LECの速習問題集でも、実技問題があります。学科学習中はSKIPした方も、実技問題に挑戦してみてくだい。
あと、過去問厳選模試の内容に、実技試験の問題があります。
頻繁に出題される問題が絞って記載されています。
こちらの模試の実技試験を完璧にすれば、合格に確実に近づけます。
一緒に勉強してみてください。
LECの「過去問厳選模試」を購入すると、CBT形式で問題の案内もあります。
また、問題に対する解説URLもついてきます。こちらの動画で学習してみてください。
あと、ほんださんの実技対策動画は少ないです。
2024-2025年度版の解説になりますが、こちらも解説が分かり易いので学習してみてください。
最後に。FP3級受験をする方へ
勉強期間の方へ
FP3級は実生活に直結する知識ばかりです。
年金や保険、税金のことなど、将来の自分のためになることを学んでいると思って取り組んでください。暗記だけでなく、『なぜそうなるのか』を理解すると記憶に定着しやすくなりますよ。
試験前の方へ
・FP3級は基礎的な内容が中心なので、落ち着いて問題を読めば必ず解けます。完璧を目指さず、6割取れれば合格です。
・深呼吸して、一問ずつ丁寧に取り組んでください。
・また、学科試験・実技試験は分からない問題は後回しにして、確実に解ける問題から取り組んでください。特に、実技試験は計算問題があるのですぐに解けない問題は後回してにして、残りの時間でじっくり取り組んでみてください。
今まで積み重ねてきた努力を信じて、頑張ってください。
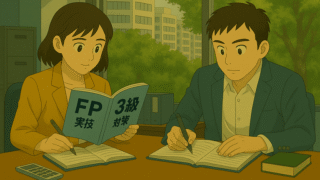
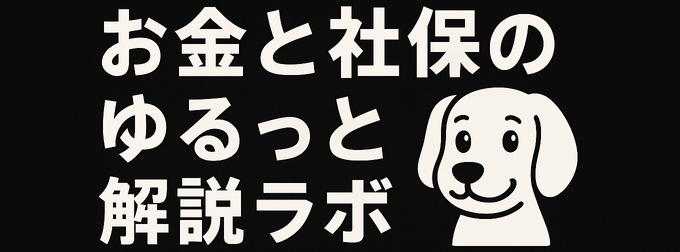
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5b5d10.9eee93d2.4b5b5d11.5915d7fc/?me_id=1213310&item_id=21553461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7917%2F9784844997917_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5b5d10.9eee93d2.4b5b5d11.5915d7fc/?me_id=1213310&item_id=21572570&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7948%2F9784844997948_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)