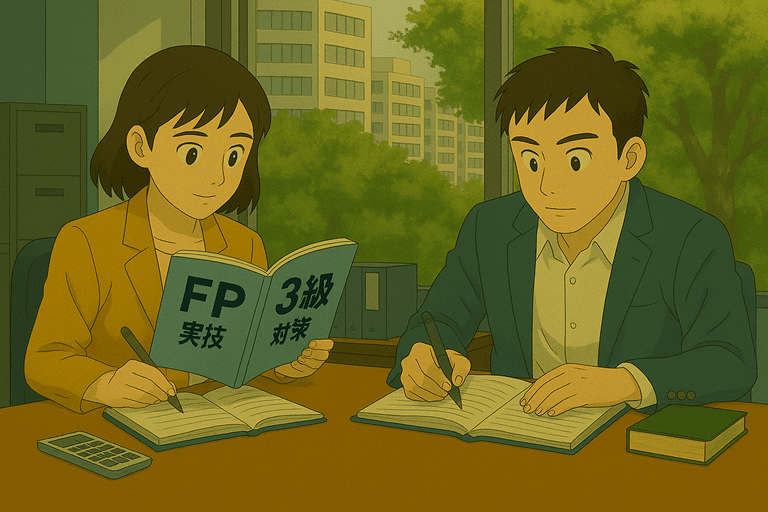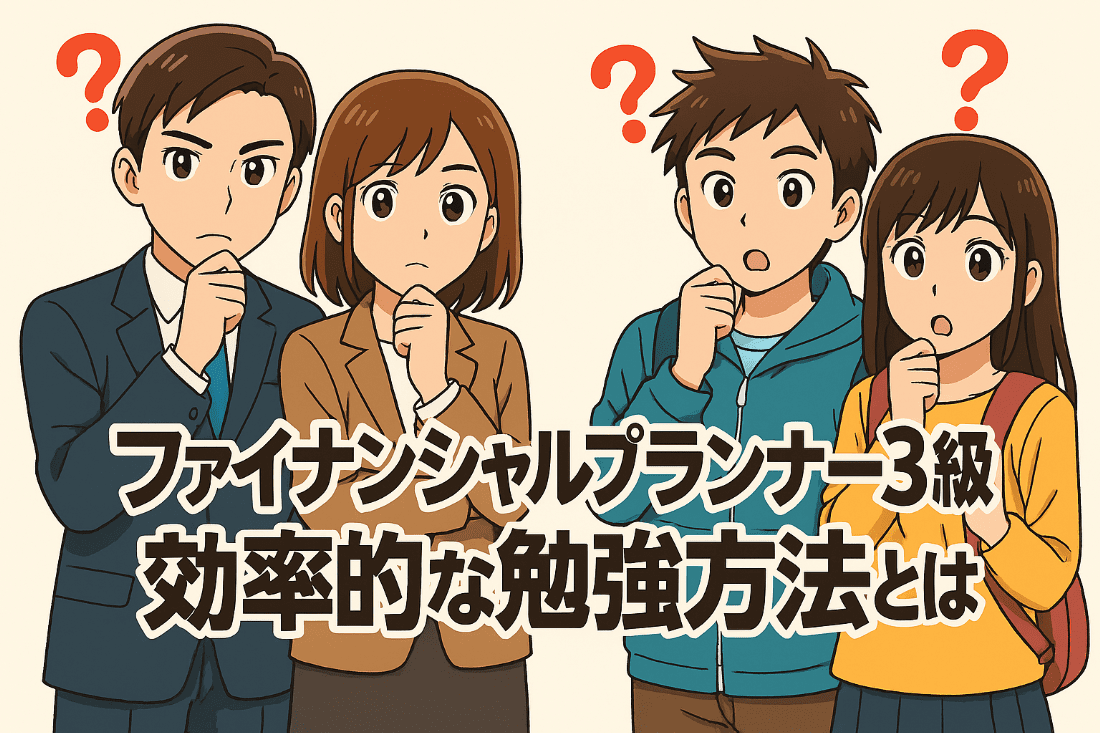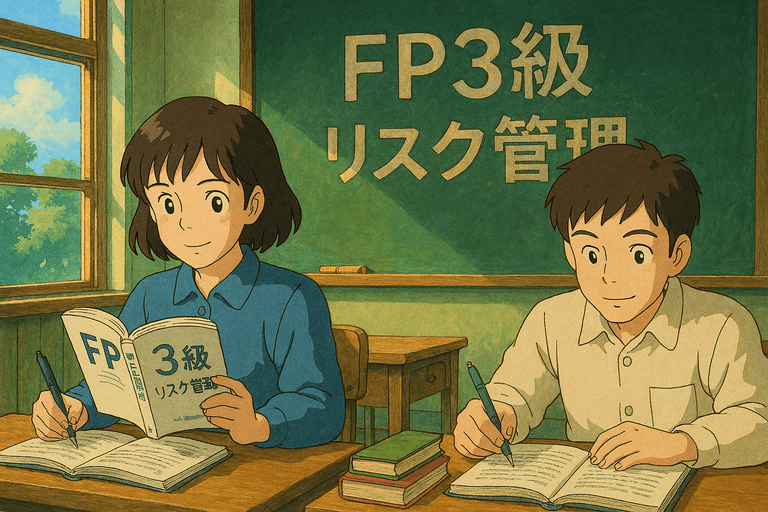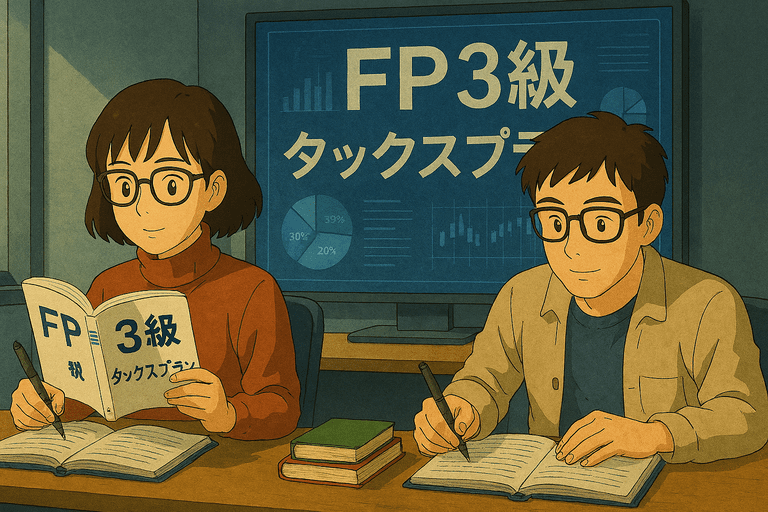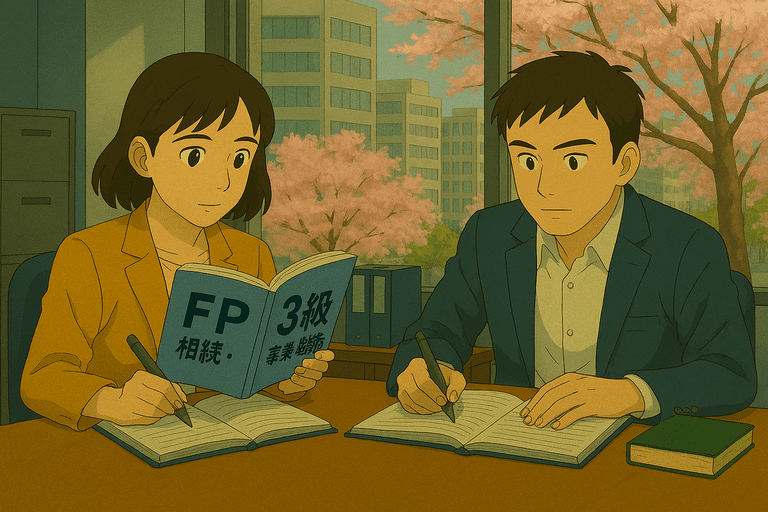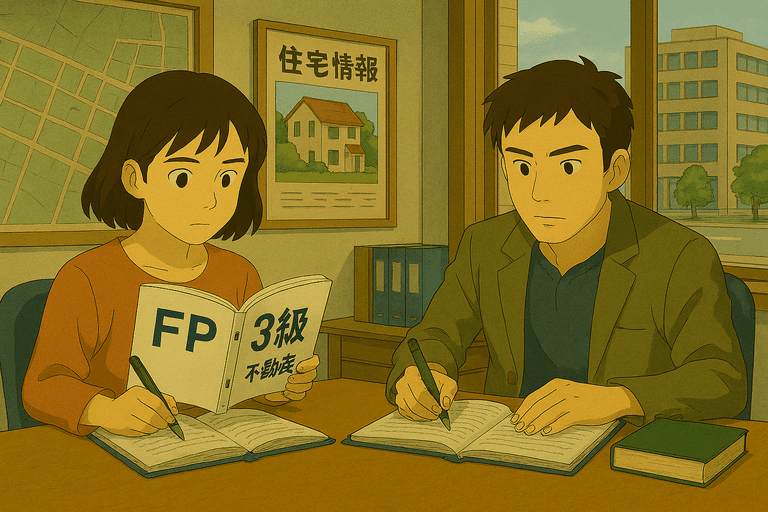FP3級 3-金融資産運用
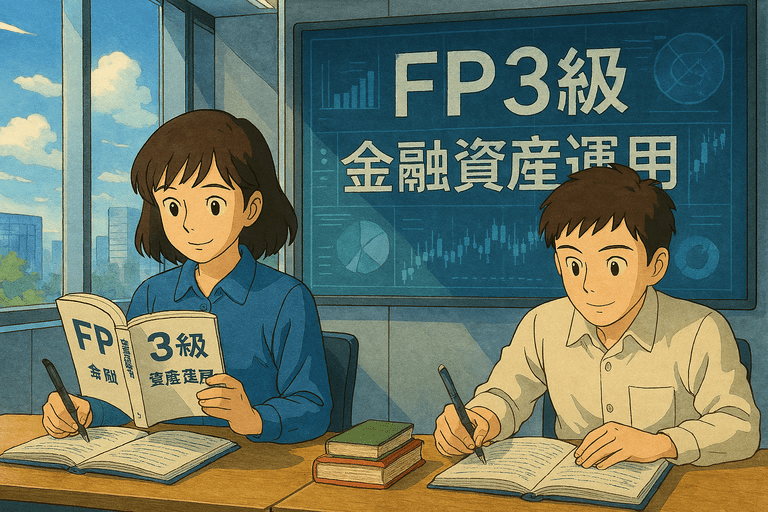
こんにちは!
FP3級の勉強を続けていますか?
混乱し始めていませんか?
まずは、理解するよりテキストや問題に慣れることを進めていきましょう!
そのうち、なんとなくFP用語が頭に入ってきます!
さて、今回は、3分野目の「金融資産管理」についてです。
今回も、ほんださんYouTubeの動画紹介前に、動画内の重要用語と感想をさらっと解説します。
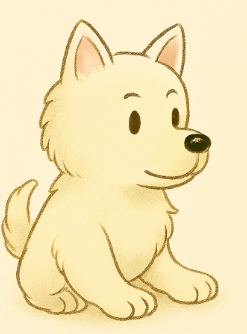
金融資産って、小金持ちになれるかもしれない
一般知識を学ぶのかな?
金融資産運用について。
金融資産の知識がつけば、株式や債券を資産にする知識が身につきます。
一般的には、日本紙幣以外に、別の金融資産を持つことは資産防衛の一つの選択肢になります。(資産ポートフォリオといいます)
今回は、金融・経済の専門用語が多くて、びっくりするかもしれませんが、ぜひ学んでみてください。
(1) 経済 景気の指標と金融政策
金融資産運用の基礎知識を解説しています。
①国の経済状況を把握するための様々な経済指標が紹介され、特にGDPの種類(名目と実質)や日銀短観、物価指数(消費者と企業)を学びます。
②景気の現状や将来を予測する景気動向指数についても、その構成要素である
・コンポジット・インデックス(CI)
・ディフュージョン・インデックス(DI)
があります。
③そして景気動向の3つのタイミングについて学びます。
・先行系列
・一致系列
・遅行系列
④マネーストックという通貨量を表す指標にも触れられます。
⑤日本銀行が行う金融政策、特に公開市場操作(オペレーション)のメカニズムが、景気調整における債券売買と通貨供給量の関係を学びます。
ニュースで聞き覚えのある単語もあると思います。ニュースがより分かり易くなるかもしれせんよ。
(2)為替と利息の計算
為替レートの変動と利息の計算方法という金融の基本的な概念を学びます。
①為替レートについては、円高と円安の仕組みについて学べます。
②需要と供給のバランスや物価、金利差がその変動要因を学びます。
③利息の計算では、
・元本にのみ利息がつく「単利」
・利息にも利息がつく「複利」
の違いを学びます。特に複利が資産運用においていかに重要であるかを具体的な計算例を交えて説明しています。
資産防衛にとって、「ドル資産」や「株の複利運用」は選択肢のひとつになります。ぜひ学んでみてください。
(3)株式投資
株式投資の基本について学びます。
①株式の売買単位や、
・指値注文
・成行注文
といった二種類の注文方法とその優先順位について学びます。
②株主になるまでの期間や、東京証券取引所のプライム・スタンダード・グロースといった市場区分といった取引のルールを学びます。
③日経平均株価やTOPIXといった市場全体の指標に加え、
PER、PBR、ROE、配当利回り、配当性向といった個別銘柄の評価指標を学びます。また、それに算出するための計算式も学びます。
本田さん特有の覚え方があるので、ぜび語呂合わせに挑戦してみてください。
(4)債券投資の基礎と、個人向け国債
債券投資の基本を学びます。
①債券は、国や企業が発行する「借金」のようなものです。投資家は債券を購入することで、期間中の利息(表面利率)と、満期時の額面金額の2つの方法で利益を得られる点を学びます。
②満期まで保有するだけでなく、途中で売買することも可能で、「利付債」と利息のない「割引債」の2種類があることも説明されています。
③個人投資家向けの「個人向け国債」については、変動10年、固定5年、固定3年という異なる期間と金利タイプがあります。また、それぞれに最低保証金利0.05%が設定されていることや、1万円から購入可能で、購入から1年後以降は途中換金もできるということも学びます。
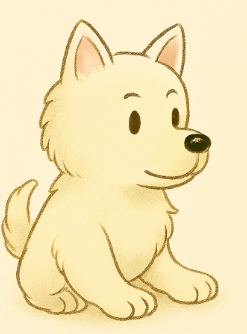
株や個人向け国債を買う場合の知識が身につきます。
国は「貯蓄」から「投資」へ動くように政策を行っています。
FPになってからも説明することが多い分野です。自分やお客様の資産形成に重要な項目です。がんばって用語を理解していきましょう!
(5)利回り計算とリスク
債券利回りの計算方法と、債券投資における主要なリスクについて学びます。
①「投資家がどのように利益を得るのか」という債券の仕組みを理解することで、最終利回りや所有期間利回りなどの計算方法を学びます。
②金利変動リスクと信用リスクという二つの主要なリスクについて、それぞれが債券価格や利回りにどのように影響するか学びます。特に信用リスクの評価指標としての格付けの重要性にも触れています。
(6)投資信託の標品と分配金
投資信託の基本的な概念と関連用語について学びます。
①投資信託は、少額から投資を始められ、専門家が複数の金融商品に分散投資を行うため、NISAなどがあります。
②投資信託の価格を示す基準価額、収益の分配である分配金(普通分配金と特別分配金の違いとその税務上の扱い)、そして購入時手数料や信託報酬といった費用についても学びます。
③投資対象(公社債投資信託、株式投資信託)や運用手法(パッシブ運用とアクティブ運用)による分類、さらにアクティブ運用における
・トップダウンアプローチやボトムアップアプローチ
・バリュー投資とグロース投資
といった投資戦略について学びます。
最近、NISA(少額投資非課税制度)がブームになっているため、知っている人は覚えやすく、知らない方は非課税制度を知るチャンスになります。
(7)ポートフォリオ・デリバディブ
外貨預金、デリバティブ取引、ポートフォリオ理論という3つの金融商品と概念について学びます。
①外貨預金では、高金利の魅力と同時に為替レートの変動リスク、特にTTS(日本円から外貨へ交換するレート)とTTB(外貨から日本円へ戻すレート)の違いと計算方法がを学びます。
②デリバティブ取引では、
・コールオプション(買う権利)
・プットオプション(売る権利)というオプション取引があります。
③ポートフォリオ理論では、複数の金融商品を組み合わせることでリスクを分散し、安定した収益を目指す考え方があります。
④さらに、異なる資産の値動きの関連度合いを示す相関係数(-1,0.1の関係)が、分散投資効果を最大化するための重要な指標として学びます。
(8)資産の保護と税務
金融資産を保護する仕組みと、投資を促進するためのNISA制度について学びます。
①銀行破綻時に預金を保護する預金保険制度や、証券会社破綻時に投資家の資産を保護する日本投資者保護基金といった、万が一の事態に備えるセーフティネットの重要性を学びます。
②これらの制度にはそれぞれ上限額があり、特に一般的な預金や有価証券は1金融機関あたり1000万円まで保護される点が重要になります。
③また、利益に対する税金が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)は重要です、2024年からの新NISAでは年間投資枠が拡大され、生涯で1800万円まで非課税で投資できるようになったこと、さらにいつでも売却可能という柔軟性があることを学べます。
これらの制度は、資産運用を考えている人々にとっても、重要な項目ばかりです。
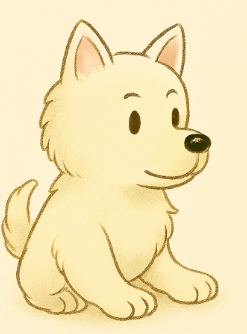
見慣れない単語が多いから頭がパニックにあるよね。
でも、学習した後に、この記事ブログを振り返ると
単語の意味が分かり始めるはず!!!
普通の文章のように読めるようになれば、
FP3級合格も近いかもね!?
ほんださんのYouTube 「FP3級 爆速講義」も視聴してみてください。
金融資産の解説も、とても分かり易いです。
講義数は8講座になります。
参考として、金融資産の学習をまとめました。
最後の学習時に、さらっと復習するときに利用してみて下さい。
動画やテキストの参照は、INPUTです。
INPUTだけでは試験は合格できません。忘れずにOUTPUTをしましょう!
あと、上ページの「大枠解説と感想」は、学習後にもう一度読み直してみて下さい。
用語の意味が分かるようになっていれば、合格に近づいているかもしれませんよ。
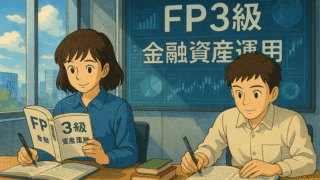
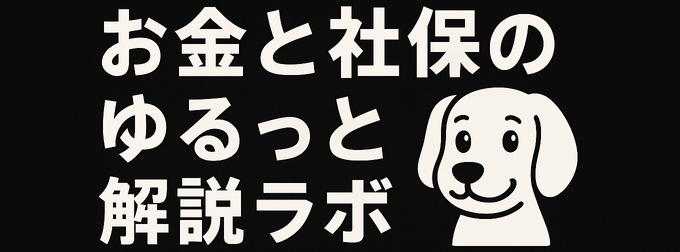
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5b5d10.9eee93d2.4b5b5d11.5915d7fc/?me_id=1213310&item_id=21553461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7917%2F9784844997917_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)