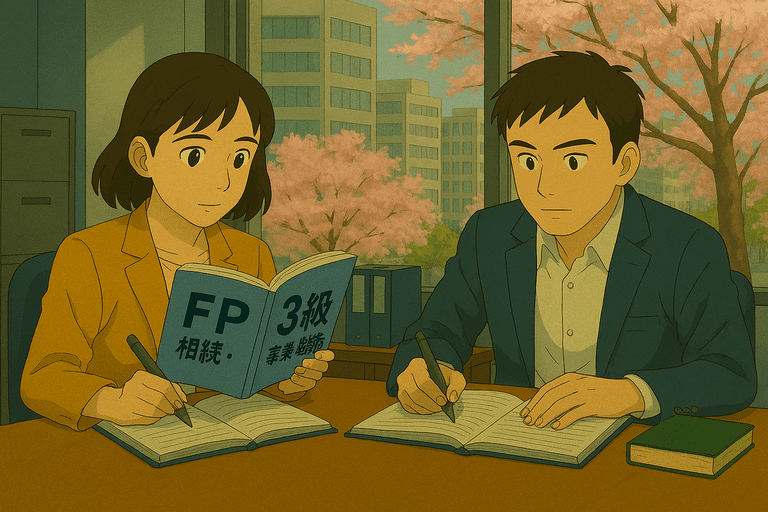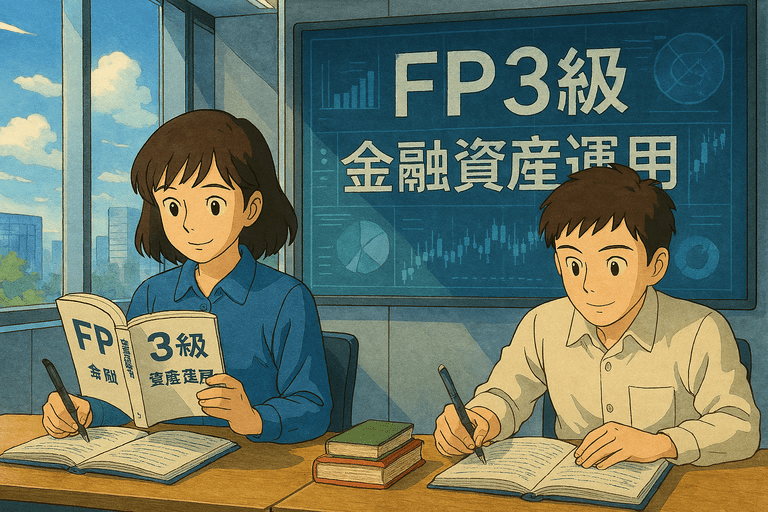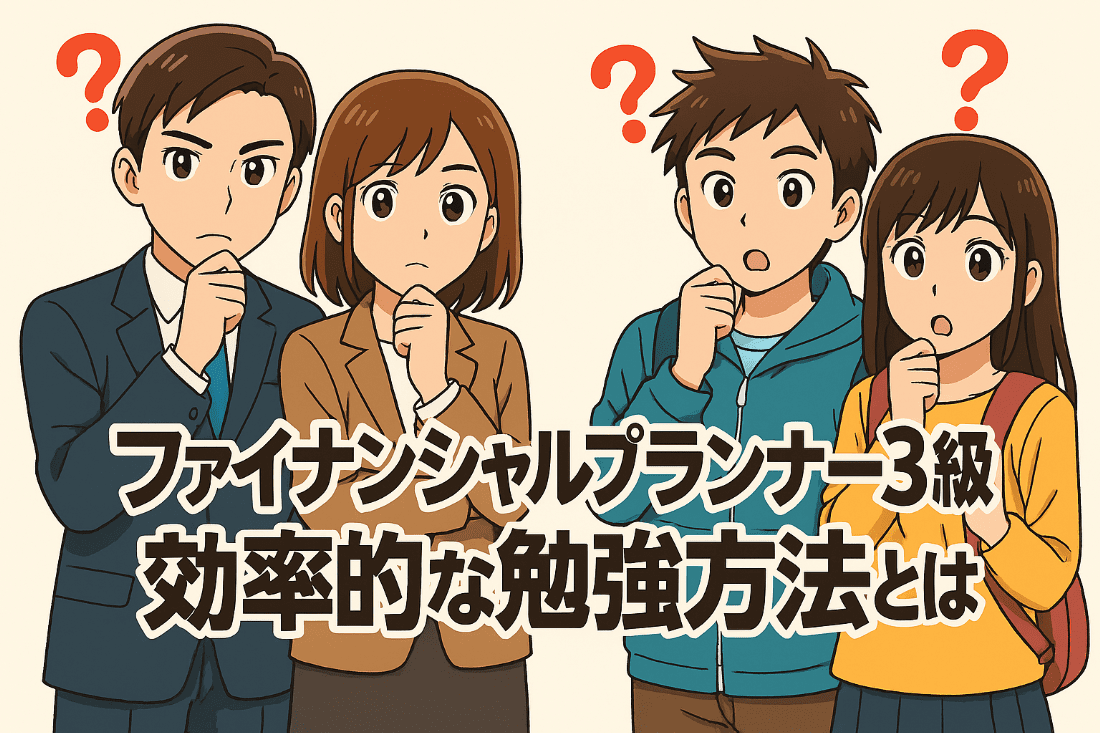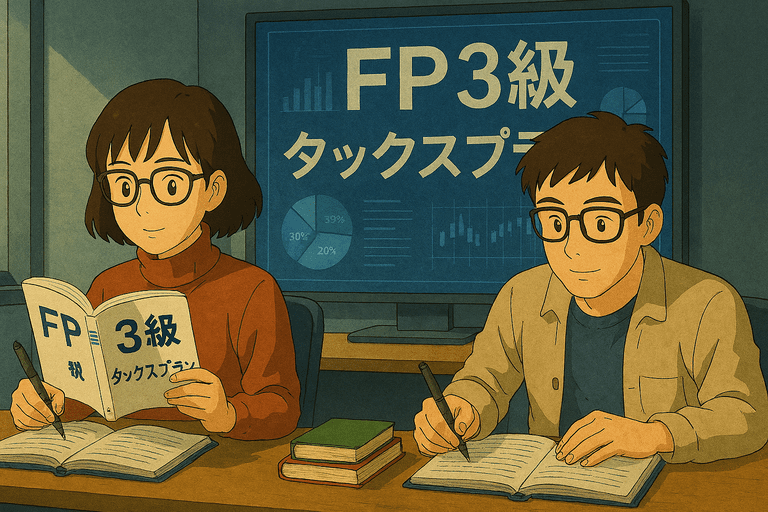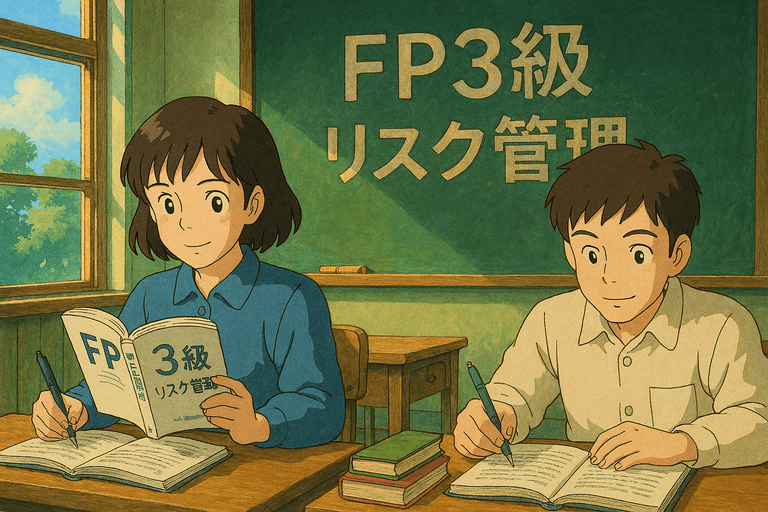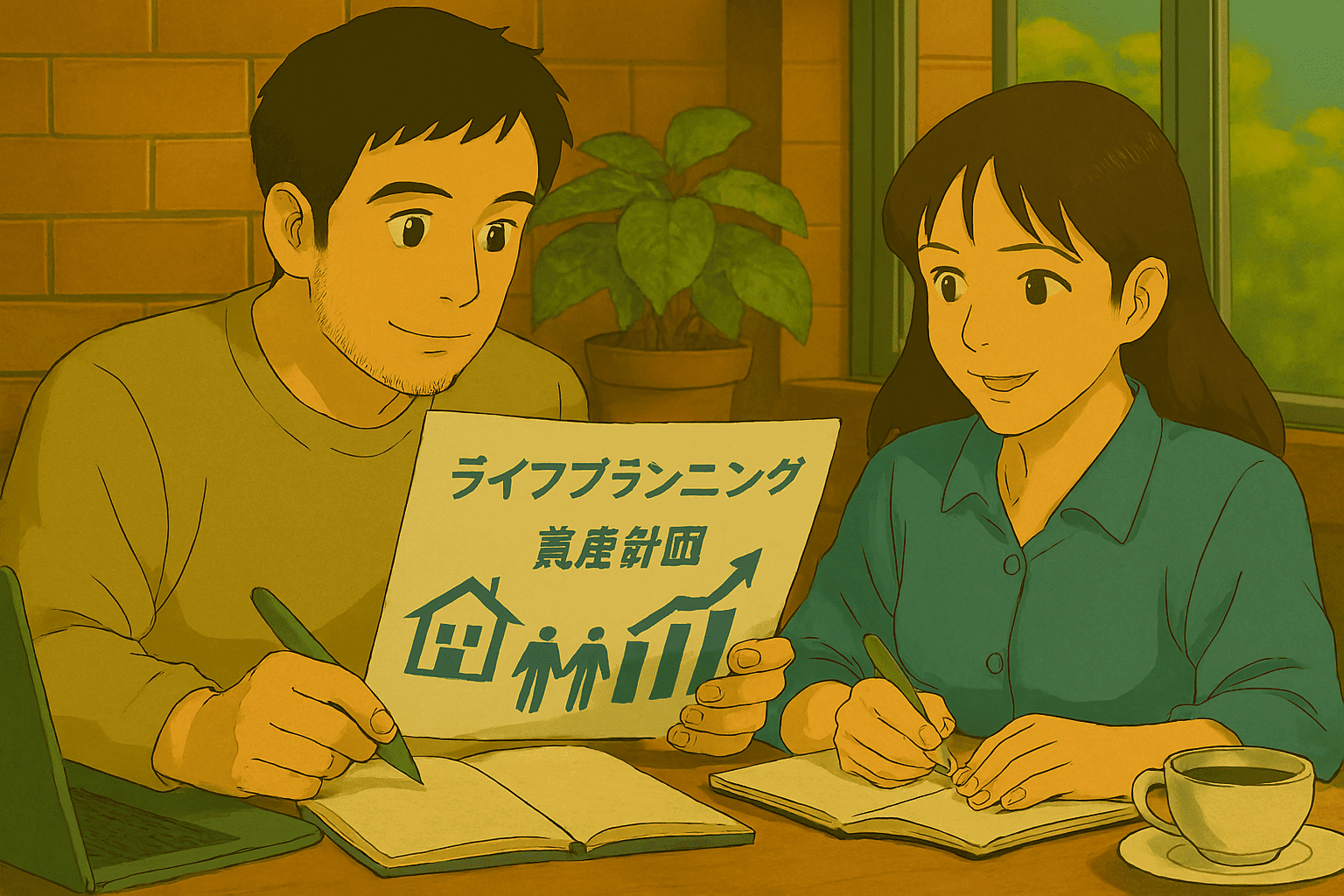FP3級 5-不動産
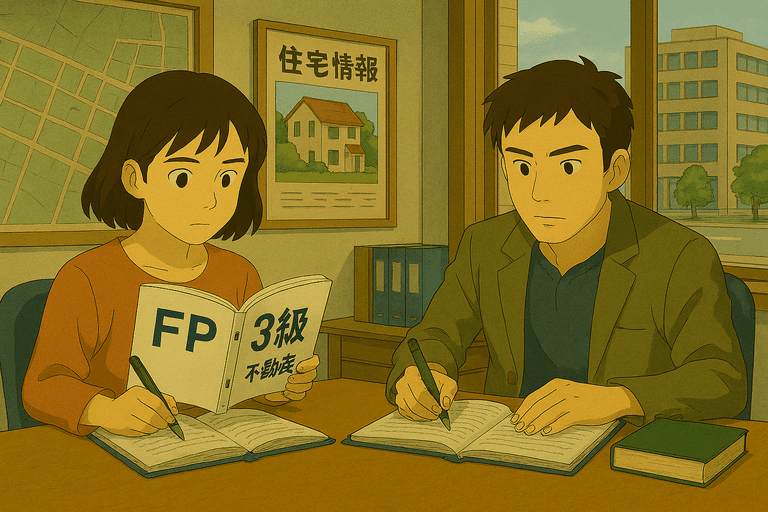
FP3級の勉強に、順調ですか?
今回は不動産の話です。
不動産とは、「土地」および「その上に建てられた建物」など、動かすことができない資産のことを指します。たとえば、家やマンション、オフィスビル、農地などが不動産に含まれます。これらは「物理的に動かせない」という特徴があり、法律上も特別な扱いを受けます。
不動産は、個人の生活に深く関わっており、住まいに利用されるだけでなく、資産としての価値も持ちます。売買や賃貸、相続などの場面では、登記制度や税金、契約のルールが重要になります。
不動産の知識は将来の住宅選びや資産形成、さらには社会の仕組みを理解するうえで役立ちます。
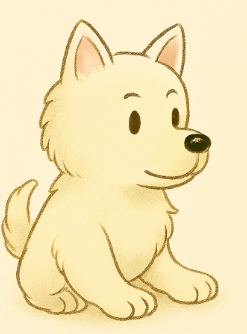
不動産は、不動産用語・権利関係・税制・価格など
関連する単語が多いから複雑だなー。
でも、建物や土地の購入は、
人生で1番高い買い物になるから、
ライフプランニングには大事だよね。
マイホーム購入以外に、賃貸契約する場合には役に立つ知識だよ。
さて、今回も、5分野目の「不動産」についてです。
ちなみに、もしも宅地建物取引主任者にも興味がある方は、内容が重複している点があります。不動産業界に興味がある方は得意分野にしていきましょう!
では、いつも通り、ほんださんのYouTubeの大枠解説と感想を記載します。
(1)不動産の登記と登記
不動産の価格評価について学びます。資産を決める方法で重要です。
①主要な価格の種類
・公示価格
・相続税路線価
・固定資産税評価額
という3つの主要な価格の種類に焦点を当てます。
それぞれの価格がどのような目的で使用され、どの機関によって決定されるのかを学びます。
②これらの価格は、公示価格を基準として、それぞれ異なる割合(相続税路線価80%、固定資産税評価額70%)で設定されます。
③固定資産税評価額が3年に一度しか改定されないといった点は重要です。
試験対策としてこれらの情報を覚えるための語呂合わせも提供されています。
(2)不動産の取引ルール
不動産取引における重要な法的ルールと契約の種類について学びます。
①宅地建物取引業法に基づき、土地や建物の売買・賃貸の仲介には原則として宅地建物取引業者の免許が必要です。
②ただし、自己物件の賃貸は例外となります。
③不動産会社を介して借り手や買い手を探す媒介契約には、3種類あります。
・一般
・専任
・専属専任
それぞれ複数業者への依頼可否、自己発見取引の可否、契約有効期間、業務処理状況の報告義務、指定流通機構への登録義務といった厳しさの度合いが異なることを学びます。
④不動産契約における手付金の役割と、契約解除時の取り扱い(買い主は手付金を放棄、売り主は手付金の倍額を支払う)、そして不動産会社が売り主の場合の手付金の上限(本体価格の2割)になります。
もしも、不動産や住宅メーカーからマイホームを購入契約する時に、手付金が必要になります。大きな金額が動きますので、将来のご自身の私生活に関わる話かもしれません。しっかり学んでいきましょう。
(3)借地借家法
借地借家法という、土地や建物の賃貸借に関するルールを定めた法律について学びます。
①借り主の保護を目的としている点が強調されています。
②住居など生活の根幹に関わる不動産の賃貸借では、貸し主が一方的に契約を終了させることが難しいという性質があります。(借り主の方が有利)
③4種類の契約形態
・「借地権」として土地を借りて建物を建てる場合の「普通借地権」
・「定期借地権」
・「借家権」として建物を借りる場合の「普通借家権」
・「定期借家権」
上記のそれぞれの特徴を学びます。
④特に、契約期間や更新の可否、および貸主が契約更新を拒否する際に正当な理由が必要かどうかが重要なポイントとなります。
(4)都市計画法・建築基準法
日本の都市計画法と建築基準法について、基本的な概念を学びます。
①都市計画法は、良好な市街地形成を目的とし、土地の利用方法に関するルールを定めています。
・建物を積極的に建てていく「市街化区域」
・自然環境などを保護し建物の建設を抑制する「市街化調整区域」
の区分が重要です、それぞれの区域の特性に応じて開発許可の要件が異なる点が強調されています。
②建築基準法は、建物の用途や高さなどを制限することで、住民の快適な生活環境を保護するためのルールを定めています。特に低層住居地域における
・絶対高さ制限
・容積制限
などが重要です。
(5)建築基準法・その他の法律
不動産に関する日本の重要な法律について学びます
①建築基準法、区分所有法、農地法のポイントを解説しています。
②建築基準法では、建物が安全であるために、
・敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接する必要がある接道義務
・火災時に延焼を防ぐための防火規制
の概念が強調されます。
③快適な住環境と防災のため行政によって定められている点があります。
・敷地に対して建てられる建物の面積の割合を示す建ぺい率
・延べ床面積の割合を示す容積率
④区分所有法ではマンションの建て替えや大規模な変更には区分所有者の一定割合以上の賛成が必要
⑤農地法では食料生産を守るため、農地を宅地などに転用する際に都道府県知事の許可が必要になることが説明されています。
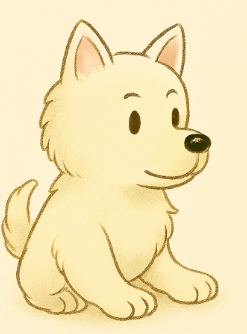
日本では法律の制限があり、建物を自由に建設できません。
もしも、土地・家・マンションを購入した後に、
「制限があって、希望の住宅にならないよ~」
と後悔しないためにも、知識武装していきましょう!
(6)不動産と税金
不動産取引に伴う様々な税金について、購入時、保有時、売却時の三つの段階に分けて学びます。
①不動産取得税は地方税、登録免許税は国税が購入時にかかります。
②固定資産税は保有時に毎年課される市町村税です。
③不動産を売却した際に生じる利益、すなわち譲渡所得には所得税が課されます。その計算方法を学びます。
④重要な特例
・5年を超える保有期間で税率が優遇される長期譲渡所得。
・マイホーム売却時に適用される3,000万円特別控除や軽減税率の特例。
について学びます。
(7)不動産の有効活用
不動産の有効活用と不動産投資の利回りについて学びます。
住宅でなく、不動産資産として活用していく内容になります。
①不動産の有効活用については
・土地の所有者が建設費用のリスクを負わずに建物を建てる「等価交換方式」
・将来のテナントから建設資金を募る「建設協力金方式」
・土地を一定期間貸し出して賃料を得る「定期借地権方式」
の3つの方法が重要です。
②不動産投資の利回りについては、
・諸費用を考慮しない「表面利回り」
・諸費用を差し引いた実質的な利益で計算する「純利回り」
の違いが重要です、
マンション投資勧誘の悪徳業者に騙されないためにも、純利回りを理解することが重要です。
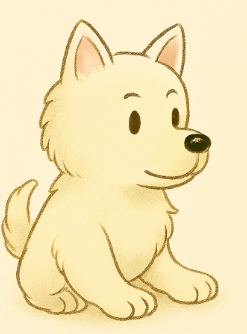
土地や建物は単なるモノではなく、
人生設計や相続、税金対策に深く関わる重要な要素です。
安心できる住まい選びや資産形成の土台を築く力を養うことができます。
これらの知識は、ご自分だけでなく、FPになったときに相談者の人生に寄り添う大切な武器となります。
不動産単語も、聞きなれない単語が多いですが、
しっかり学んでいきましょう!
ほんださんのYouTube 「FP3級 爆速講義」も視聴してみてください。
ほんださんの解説ならば、不動産の話も楽しく学習できます。
講義数は7講座になります。
ほんださんの楽しい講義の受講後は、
OutPutの学習も忘れずに!
あと、上ページの「大枠解説と感想」は、学習後にもう一度読み直してみて下さい。
単語の意味が分かるようになっていれば、合格に近づいているかもしれませんよ。

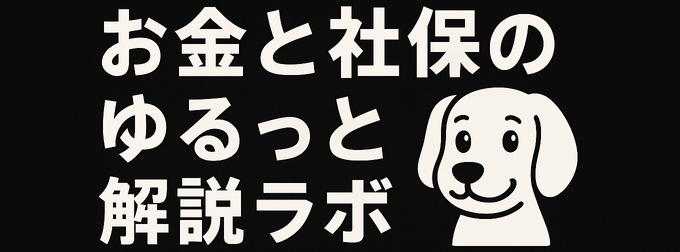
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5b5d10.9eee93d2.4b5b5d11.5915d7fc/?me_id=1213310&item_id=21553461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7917%2F9784844997917_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)