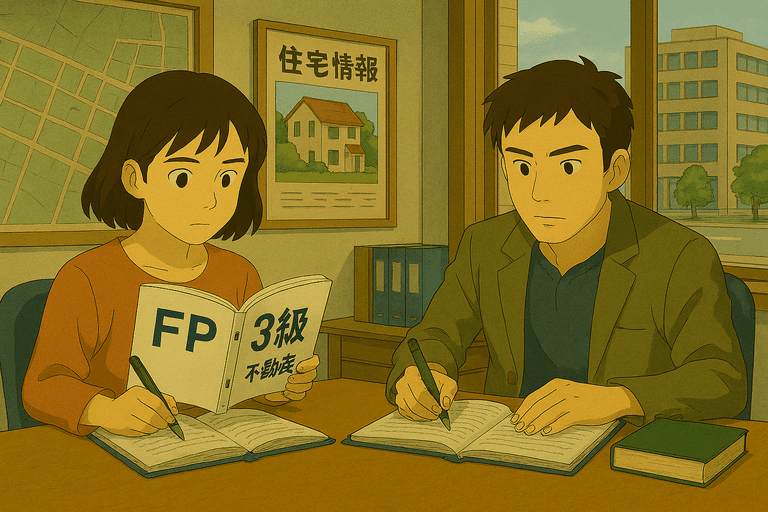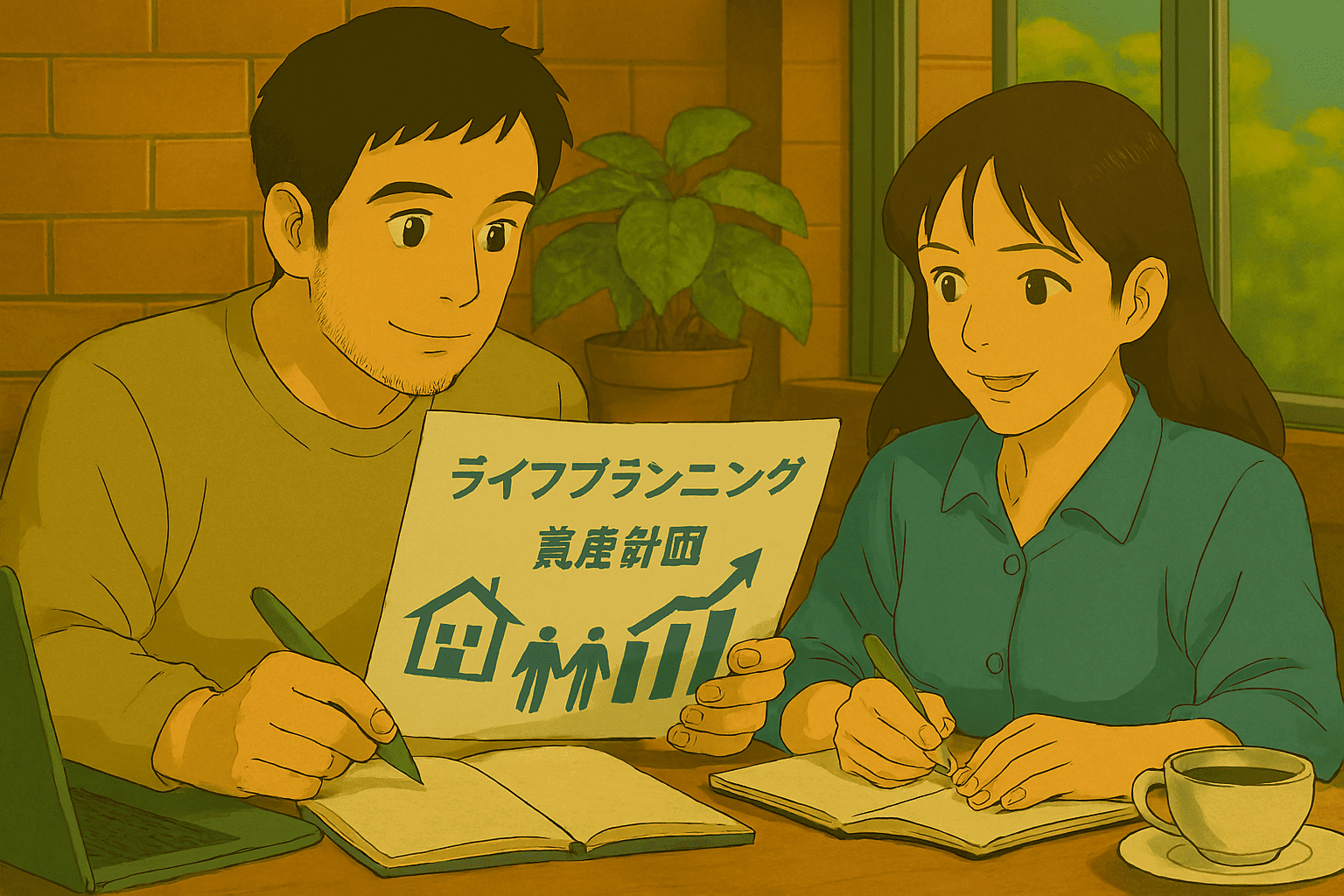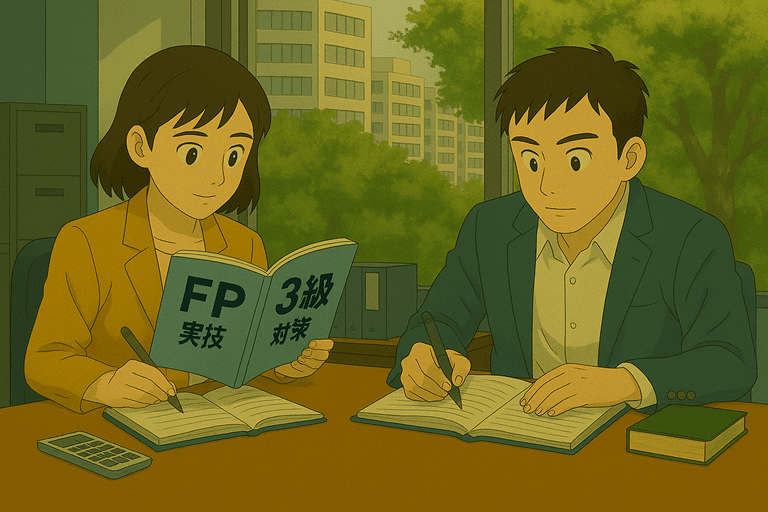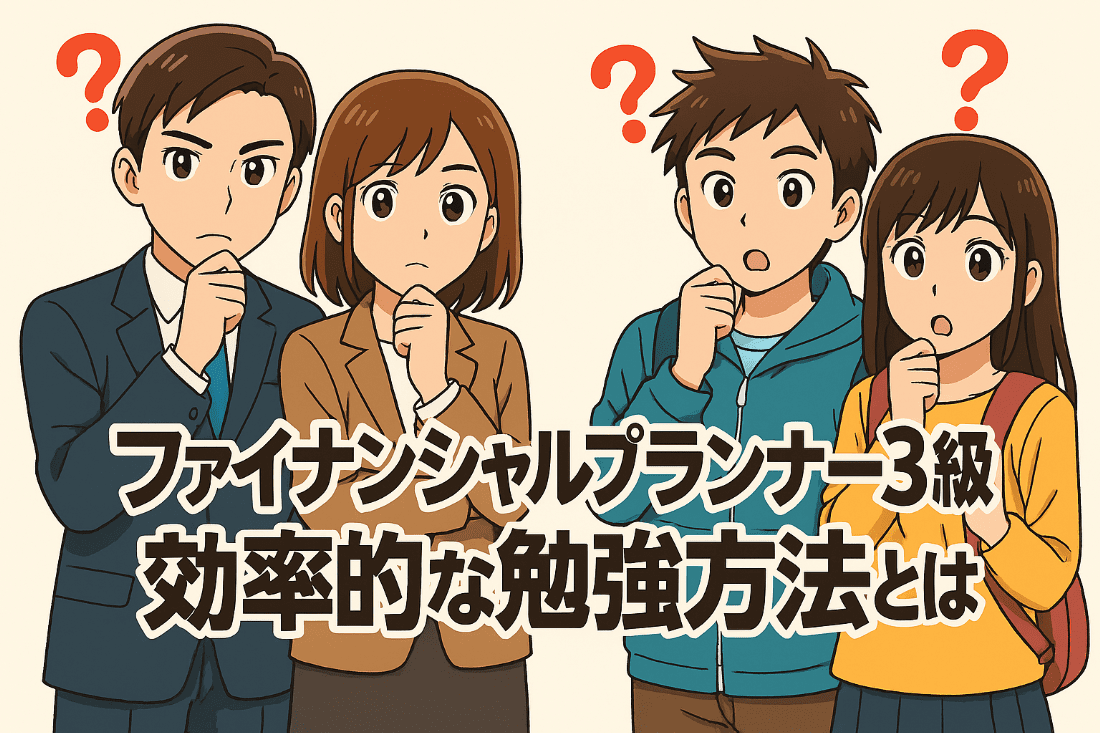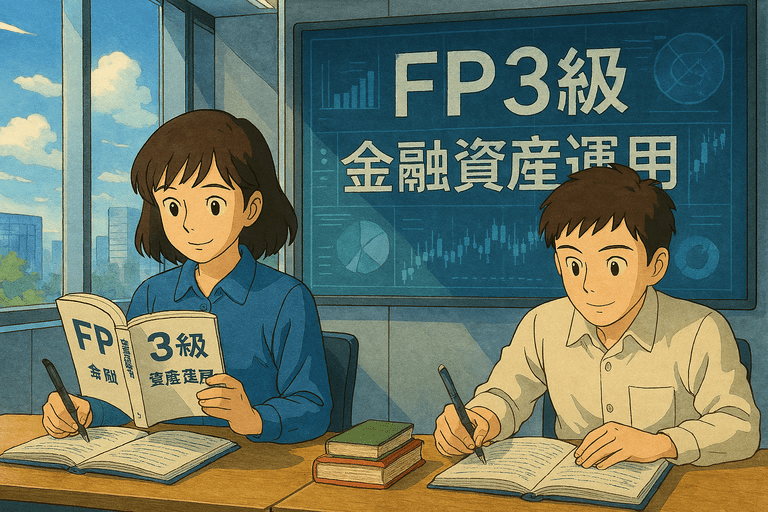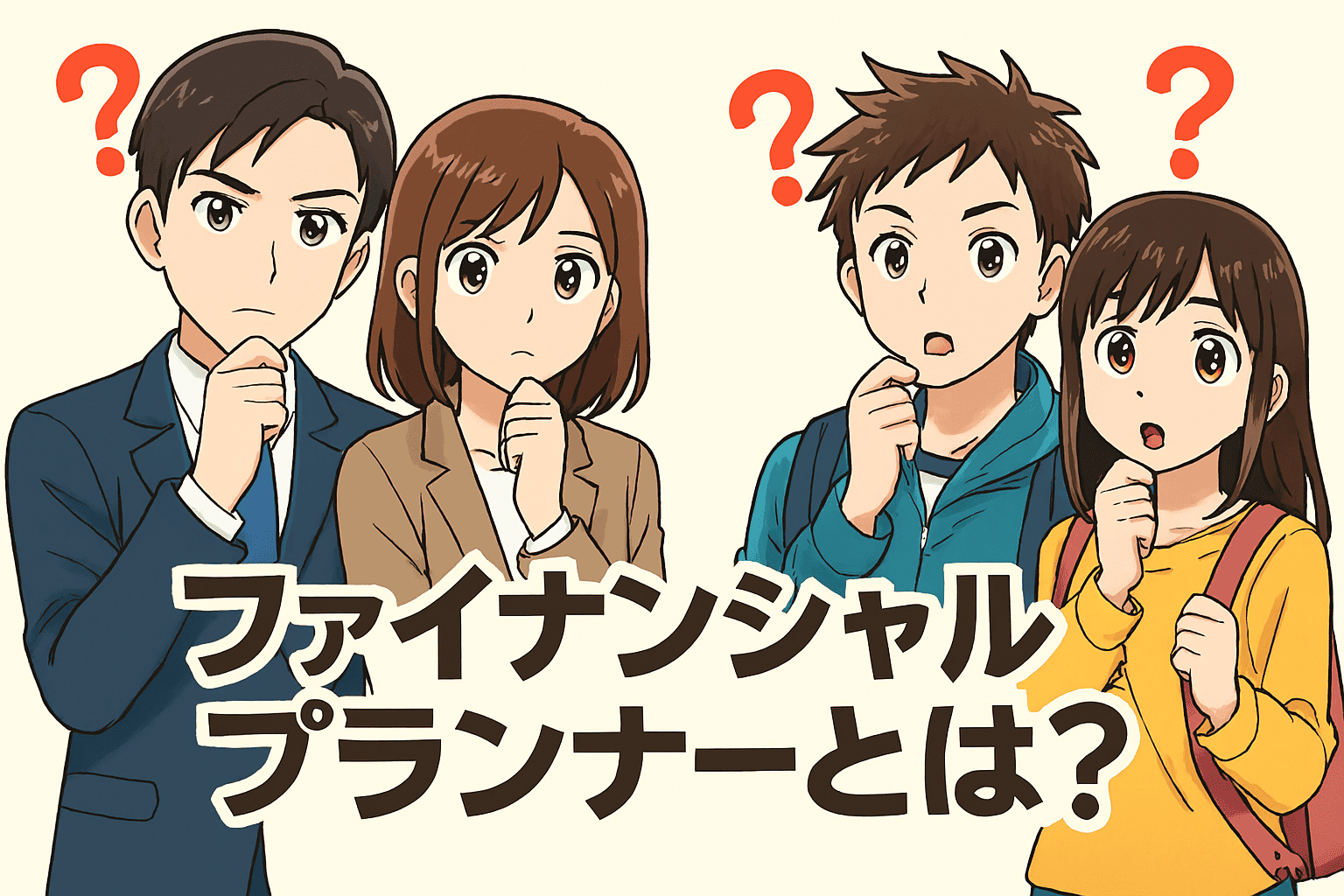FP3級 6-相続・事業継続
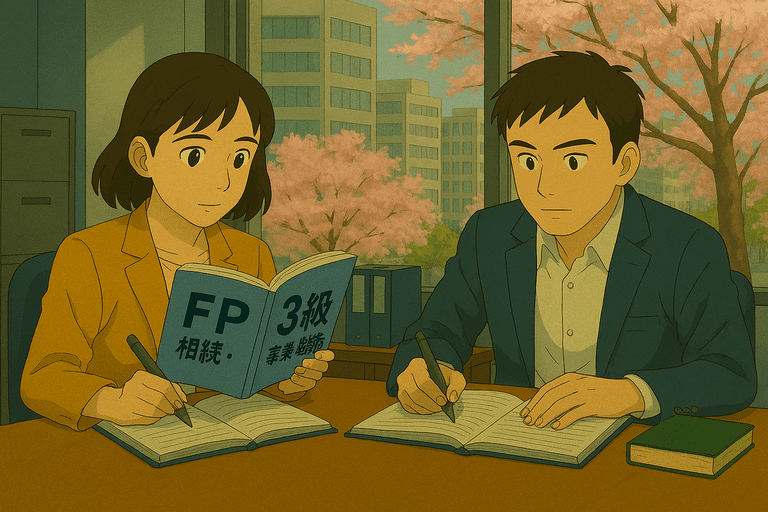
今回は相続・事業継続の話です。
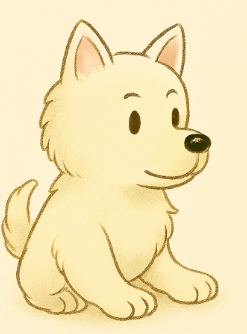
相続・事業継続。
ちょっと未来の話で実感がないー。
でも、何か大きなお金が動きそうな匂いがする。
「相続・事業継続」というテーマはまだ遠い未来の話に感じるかもしれません。しかし、FP3級のこの科目を学ぶことで、親世代の相続や自分たちの将来設計に備える力が身につきます。特に、住宅購入や子育て、親の介護などライフイベントが重なる世代の方こそ、相続や事業承継の知識を早めに理解しておくことで、家族の安心と資産の守り方が見えてきます。
年配の方にとっても、人生の終盤や事業の引き継ぎに関わる重要なテーマを扱う分野であり、家族や企業の未来を見据えた計画に直結する知識が詰まっています。
この科目を学ぶことで、単なる制度理解を超えて、人間関係や感情の機微に寄り添ったアドバイスができるようになります。
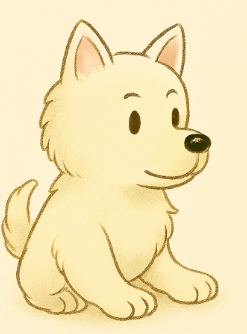
相続・事業継続は、
他科目の知識を統合する“集大成”的な位置づけにあります。
特に、税務・保険・不動産の知識が複合的に求められるため、他科目の理解が深まるほど、この科目の学習効果も高まるらしいよー
総合的に求められる点は?
①タックスプランニング
- 所得税・贈与税・相続税の連携理解が必要
- 控除や特例の使い分けが、相続税の節税に直結
② リスクマネジメント
- 生命保険の受取人設定や死亡保険金の非課税枠など、相続時の保障設計に関係
- 死亡保険金を活用した納税資金の準備など、実務的な活用が可能
③ 不動産
- 土地・建物の評価、共有名義の処理、相続登記など、実務的な連携が多い
- 小規模宅地の特例や不動産の分割方法など、税務と法務の両面で重要
FP業務の総合力を測る重要な分野です。「相続・事業継続」の学習しなががら、他科目を振り返って復習すると理解が深まります。
では、いつも通り、ほんださん動画の解説と感想を記載します。
(1)FP3級試験の相続・事業承継分野について
死亡により相続が発生した場合に、誰が相続の権利(相続人になるかどうか)があるかを学びます。
①法定相続人の定義と順位
②法定相続分の計算方法。
相続が発生した場合の財産分配のルールを理解するために、被相続人(亡くなった人)と相続人(財産を受け継ぐ人)という用語を学びます。
また、配偶者は常に相続人になること、そして子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続の優先順位があることが強調されています。
③代襲相続や養子縁組の種類(普通養子と特別養子)が相続に与える影響
④法定相続分の割合の具体的な計算例を学びます。
(2)遺産相続における重要な手続きと概念
遺産が発生した場合の相続の手続きを学びます。
ドラマで、相続問題で家族関係に亀裂が発生する物語がよくあります。相続発生前に以下の内容を知っておくと、家族間の亀裂を予防できるかもしれません!?
①遺言による指定分割、または相続人全員の合意に基づく協議分割といった遺産分割の方法を学びます。また、法定相続分はあくまでも目安であり、相続人全員の合意があれば自由に分割できる点が強調されています。
②相続の承認(単純承認・限定承認)と放棄について触れ、特に相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があると述べられています。
③遺言については、15歳以上であれば作成可能であり、自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類が詳しく紹介され、それぞれの特徴や作成時の注意点、検認の要否が比較されています。
④遺留分の概念が解説されており、遺言で特定の人物に全財産を譲ると定められていても、配偶者や子供、直系尊属には最低限の相続財産を受け取る権利(遺留分)が認められていることが、計算例を交えて説明されます。
(3)相続税の計算方法
課税価格の算出から納税までの手順を学びながら、相続税の全体像を理解します。
①相続税がかかる財産(預貯金、不動産、みなし相続財産など)と、
かからない財産(墓地、仏壇、一定額までの生命保険金など)を区別し、
そこから負債や葬式費用を差し引いて課税価格を求めます。
②基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を引いて課税遺産総額を算出し、具体的な税額計算へと進みます。
③さらに、配偶者控除や2割加算といった特例が適用されるケースがあります。
④相続税申告の期限と提出先、納税方法についても学びます。
(4)贈与の基礎知識と贈与税
今度は、生きている方からお金をもらった(贈与)話になります。
贈与とその税金について学びます。
①贈与は個人から個人へ財産を無償で渡す契約であり、贈る側を「贈与者」、受け取る側を「受贈者」と呼びます。
②贈与は口約束でも成立しますが、書面によるかどうかで解除の可否が変わります。
③死亡時に財産を贈与する「死因贈与」は遺言とは異なり双方の合意が必要で、相続税の対象となります。
④贈与税の計算では、「みなし贈与財産」という実質的に贈与とみなされるものがあり、通常の価格より著しく低い金額で財産を売買した場合などの差額が対象になります。
⑤贈与税の基礎控除額は年間110万円で、これは受贈者ごとに適用される点が重要です。
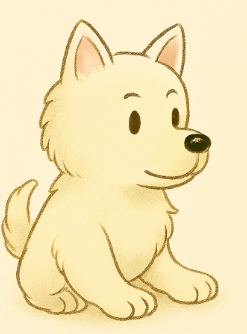
金銭に余裕がある家族は、
親から子へ⑤贈与税の基礎控除を利用しているらしいよー
(5)贈与税における特定の非課税制度
①夫婦間の居住用不動産の贈与に関する配偶者控除を取り上げ、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで非課税となること、婚姻期間20年以上の夫婦に限定される点が強調されます。
②相続時精算課税制度について、年間110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までが非課税となり、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の推定相続人への贈与に適用されること
③贈与時点では非課税でも相続時に合算されて課税される仕組み
④住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金といった特定の用途に限定された贈与の非課税制度が紹介され、これらの制度は他の控除と併用可能である点が述べられています。
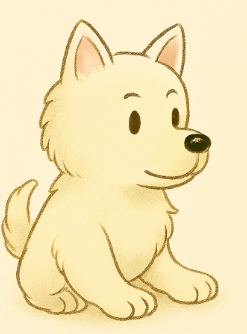
住宅関連の贈与制度は、利用している方が多いよ。
住宅を購入する人は要チェックだね。
試験でもよく出題されるよー。
(6)相続財産の評価
相続税や贈与税を計算する際に必要となる財産の評価方法について学びます。
相続財産の価値を正しく把握するために重要なテーマになります。
①宅地の評価に焦点を当て、
・路線価方式や倍率方式
・小規模宅地の特例など、
計算方法や適用条件を学びます。
②上場株式や生命保険の評価についても触れ、それぞれの評価額の決定基準を学びます。
ほんださんのYouTube 「FP3級 爆速講義」を視聴してみてください。
ほんださんの解説ならば、相続・事業継続の話も楽しく学習できます。
講義数は6講座になります
ほんださんの楽しい講義の受講後は、
OutPutの学習も忘れずに!
あと、上ページの「大枠解説と感想」は、学習後にもう一度読み直してみて下さい。
単語の意味が分かるようになっていれば、合格に近づいているかもしれませんよ。
全学科目が終了しました
| 科目名 | 内容の概要 |
|---|---|
| ① ライフプランニングと資金計画 | 社会保険、年金、教育資金、住宅資金など、人生設計に必要な資金の知識 |
| ② リスク管理 | 生命保険、損害保険、医療保険など、万が一に備える保険の仕組み |
| ③ 金融資産運用 | 株式、債券、投資信託などの金融商品の基礎知識と運用方法 |
| ④ タックスプランニング | 所得税、住民税、控除制度など、税金に関する基本的な知識 |
| ⑤ 不動産 | 不動産の売買、賃貸、登記、税金などの基礎知識 |
| ⑥ 相続・事業承継 | 相続税、贈与税、遺言、事業承継の基本的な知識 |
相続・事業継続を学習した後、リスク管理(保険)、タックスプラン(税金)・不動産を復習すると、より知識が深まります。
さて、学科科目が終了したので、次は実技試験対策が必要です。
計算問題を解く場面も多くなります。本当に学んで事が理解できているか試されます。
次回の実技試験対策にも、取り組んでいきましょう!!
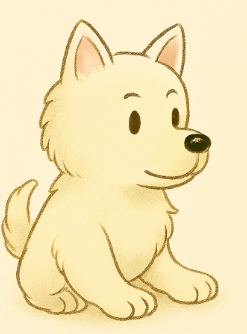
CBT試験だから、本試験では、電卓は利用できないよ。
でも、実技試験の勉強時は、
電卓(スマホ電卓もOK)を利用して学習してね。
電卓計算にも慣れる必要がありますよー
暗算の場合、計算ミスするリスクがありますので。。
(久しぶりの掛算、割り算は頭が固まりますよー)
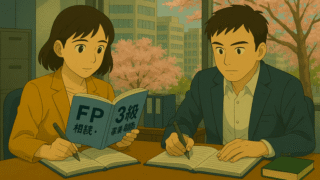
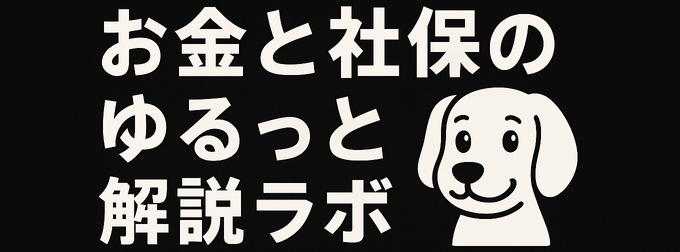
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5b5d10.9eee93d2.4b5b5d11.5915d7fc/?me_id=1213310&item_id=21553461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7917%2F9784844997917_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)